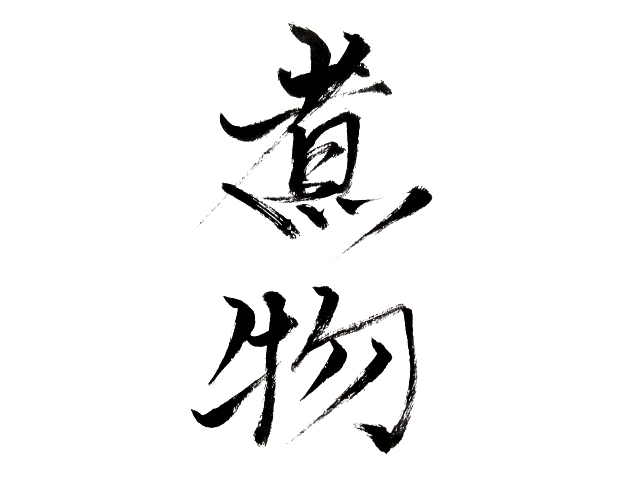穂垂れ煮染め(ほだれにしめ)
和食の煮物、料理用語集
穂垂れ煮染め(ほだれにしめ)とは
鹿児島県の郷土料理で、九州地方には「穂垂れひき(穂垂れ吹き、または穂垂れ節句)」という、小正月の年越しにあたる1月14日を祝う行事があります。
これは、穂が長く垂れるように豊穣(ほうじょう)を願って行われる農家の祭りで、このときに作られる煮物料理が「穂垂れ煮染め」です。
調理方法
■ 材料には大根、人参、青菜、椎茸、じゃが芋等の野菜類と共に揚げ豆腐、塩魚などを使い、包丁をできるだけ入れずに穂のような長いままの状態で調理して、味噌と砂糖で味をととのえて煮込んだあと、大きな丼に盛りつけます。
≫煮染め(にしめ)の語源と意味
【関連】
≫おせち料理に、ごぼうを使う理由
≫おせちに数の子とにしんを使う理由
≫数の子のうす皮むきと下処理のコツ
数の子の塩抜き方法と薄皮をむくときの「簡単なコツ!」今回は、おせち料理や祝い膳によく使う数の子の下ごしらえをご紹介したいと思いますので、正月の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。数の子の薄皮をむくのは手間と時間がかかって大変な作業ですが、コツをつかむとむきやすくなります。
≫おせち料理に鰤(ぶり)を使う理由
≫ぶりの照り焼きを作る時の配合と割合
≫焼き物のつけだれ、かけだれ割合一覧
≫おせち料理や
正月に関連した調理内容一覧
≫おせちと正月に関連した
【料理の雑学、豆知識一覧】
おせち料理に込められた幸福になるための願いと理由につきましては≫「おせちの食材がもつ語源集、意味、由来8つ」に掲載しております。
【1月7日の七草がゆ】
≫春の七草の種類と特徴
~では、秋の七草とは?
【1月15日の小豆(あずき)がゆ】
≫1月15日に小豆がゆを食べる理由
【野菜の切り方】
≫おせち料理に使える飾り切り一覧
≫梅人参の切り方とねじり梅の手順
≫松の葉で簡単に作れる箸置きの手順
≫煮物に使える野菜の切り方とコツ
【参考】
≫料理別の簡単な調味料割合一覧表へ
≫煮物レシピの関連(姉妹サイト)
【煮物の料理用語集50音一覧】今回は煮物に関連した「語源、意味、由来」などを料理別に整理いたしましたので、煮物の献立や和食調理の参考にされてはいかがでしょうか。■各煮物や調理法に移動いたします。
【他の料理用語集】
≫献立別の料理用語集まとめ
【語源、意味、由来一覧を見る】
≫料理の語源、意味、由来50音順一覧へ
【和食の献立集】
≫煮物の献立一覧を見る
≫季節別、旬の食材一覧へ
煮物や他の料理に使える飾り切りにつきましては≫「飾り切り方法【100選】基本手順と切り方のコツ!」に掲載しておりますので参考にされてはいかがでしょうか。